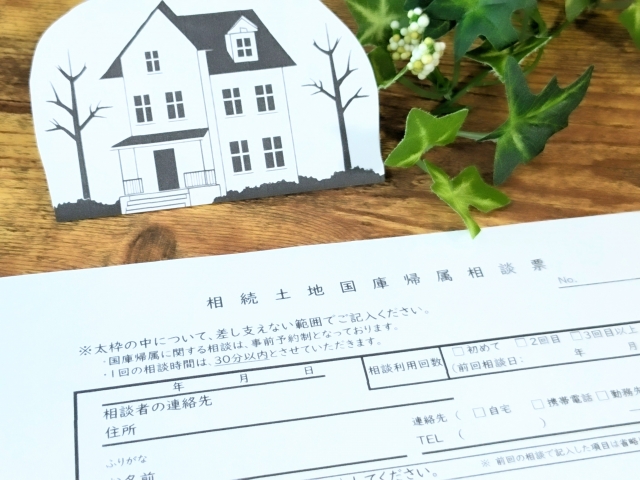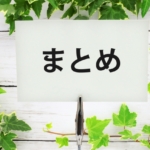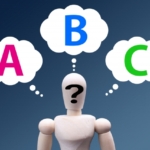相続国庫帰属制度で不要な土地を国に引き渡す方法
親から相続した土地が 使い道のない別荘地や原野、山林 だった場合、
相続人にとっては「負の遺産」になりかねません。
売却や民間での引き取りが難しい土地を処分する方法として、
近年注目されているのが 「相続土地国庫帰属制度」 です。
この記事では、制度の仕組みや対象となる土地、
メリット・デメリット、手続きの流れを詳しく解説します。
1. 相続国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月に始まった新しい制度です。
相続や遺贈によって取得した土地について、
一定の条件を満たせば国が引き取ってくれる 仕組みになっています。
-
・不要な土地を国に引き渡せる、
-
・将来にわたって固定資産税や管理費の負担から解放される、
-
・子どもや孫に「負の遺産」を残さずに済む、
特に、売却が困難な山林や原野などを相続した人にとって、
大きな救済策となり得ます。
詳細は以下をご確認ください。
◉相続国庫帰属制度について(法務省HPより)
→ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
2. 対象となる土地と対象外の土地
対象となる土地
-
・建物が存在しない土地
-
・境界が明確で、権利関係に問題がない土地
-
・国が管理できる状態の土地
対象外となる土地
-
・建物が残っている土地
-
・担保権や抵当権が設定されている土地
-
・他人の権利が混在している土地(借地権、通行地役権など)
-
・境界が未確定の土地
-
・形状が著しく不整形で管理が困難な土地
つまり「誰が見てもトラブルなく国が管理できる土地」でなければ、引き渡すことはできません。
3. 手続きの流れ
-
申請
法務局に申請し、必要書類を提出します。 -
審査
国が土地の状態を確認し、要件を満たしているか審査します。 -
負担金の納付
承認された場合、申請者は「管理費用の一部」として負担金を納付します。 -
国への引き渡し
所有権移転登記を行い、正式に国が土地を引き受けます。
この手続きには数か月かかることもあるため、早めの申請が望まれます。(審査期間の想定8ヶ月)
4. 負担金の目安
申請が承認された場合、所有者は「負担金」を国に支払います。
これは、国が将来的に管理するコストの一部を所有者が負担するという考え方です。
原則は20万円ですが、種目や区域などの条件により異なります。
また申請時に審査手数料として土地1筆あたり14,000円がかかります。
詳しくは以下をご覧ください。
◉相続土地国庫帰属制度の負担金(法務省HPより)
→ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
5. 制度を利用するメリット
-
・売れない土地でも処分できる
-
・相続人がいなくても“宙に浮く土地”を残さない
-
・固定資産税や管理費から完全に解放される
-
・国が正式に引き取るため安心感がある
6. 制度を利用するデメリット・注意点
-
・すべての土地が対象ではない
-
・負担金が発生する
-
・承認されるまで時間がかかる
-
・境界確定や測量が必要になる場合がある
「国が引き取ってくれるなら安心」と思っても、条件が厳しいため事前の確認が欠かせません。
7. 他の方法との比較
-
・売却:需要があれば最も有利に処分できるが、売れない可能性あり
-
・民間引き取り:費用を払えば処分できるが業者次第
-
・相続国庫帰属制度:条件を満たせば国が引き取る安心感があるが、審査が厳しい
どの方法が適しているかは、土地の状態・場所・家族の希望によって異なります。
まとめ|「国に返す」という新しい選択肢
相続国庫帰属制度は、不要な土地を国に引き渡せる画期的な仕組みです。
ただし対象外の土地も多いため、「まずは自分の土地が対象になるのか」 を確認することから始めましょう。
不要な土地を放置すれば、税金や管理の負担を背負い続け、子どもに迷惑をかけることになります。
この制度も含め、早めに処分の選択肢を整理しておくことが、将来の安心につながります。
👉 次回は「不要な土地をどう処分するかの判断基準」について解説します。
👉 続けて読みたい記事
不要な土地をどう処分するかの判断基準|売却・引き取り・国庫帰属